
- この記事はこんな人におすすめ
-
- 自分の体質に合う漢方薬を見つけたい人
- 漢方薬の効果を最大限活用したい人
- 漢方薬の効果が実感できていない人
- 漢方薬を選ぶ判断材料を知りたい人
漢方薬の説明などでよく目にする「証(しょう)」とは、あなたの身体が病気や不調とどのような戦い方をしているのかを知り、どのような漢方薬が最も効果的かを見つけるためのガイドライン(指標)のようなものです。
たとえば、次のようなポイントで判断します。「冷え」「ほてり」のどちらを感じるか、病気への抵抗力が「高い」か「低い」か、強い漢方薬の処方が「向いている」か「向いていない」かなど、本記事では、東洋医学で最も大切にしている「証」について、各「証」に当てはまる人の特徴や最適な漢方の選び方、具体例、病院などでの診断方法などを、初心者の方にも分かりやすく詳しく解説します。
自分に合う漢方薬を見つけたい、しっかりと活用したいという方は、ぜひ参考にしてくださいね。

(薬剤師:5年)
漢方薬における「証」は、その人に合う漢方薬を見つけるための最重要要素の1つです。症状だけから漠然と漢方薬を選ぶよりも、「証」に合う漢方薬を選ぶ方が、副作用などの心配が少なく安心して服用できます。より早く漢方薬の効果を実感できることもあるので、しっかりと「証」についての知識を身につけましょう。
- この記事を読むとわかること
-
- 「証」の種類と当てはまる人の特徴
- 「証」と漢方薬の関係や具体例
- 「証」の診断方法や流れ
- 自分の証を知る方法
十味敗毒湯(じゅうみはいどくとう)で肌トラブルを改善!
十味敗毒湯(じゅうみはいどくとう)は、肌トラブルの治療に広く使われる漢方薬です。日焼けや乾燥などによる肌荒れ、ニキビといったことが気になるときには、十味敗毒湯を服用してキレイな肌を保ちましょう。
十味敗毒湯について詳しくはこちら

こんなお悩みございませんか?
- 自分の症状に効くのか心配
- 効果が出るのにどれくらいかかる?
- 他の薬と併用して飲んでも大丈夫?など
漢方の分野に特化した薬剤師が対応します
購入前、購入後で気になることがあれば、お問い合わせください
「証(しょう)」とは?

「証(しょう)」は、漢方医学(漢方)において最も重要な概念の一つで、専門的には次のように定義されています。
「患者が現時点で現している症状を基に、気血水、陰陽、虚実、寒熱、表裏、五臓、六病位などの基本概念を通して認識し、さらに病態の特異性を示す症候をとらえた結果を想像して得られる診断であり、治療の指示である」
分かりやすく説明すると、「証」とは、人それぞれの以下の事柄を総合的に表す指標のことです。
- 体質(生まれ持った身体の特徴)
- 身体の抵抗力(病気に対する強さ)
- 病気の原因(なぜその不調が起こったか)
- 症状の現れ方(どのような形で症状が出るか)
漢方では、病気の名前そのものよりも、個々人の体質や現在の状態に合わせた治療を重視しており、その人に最も適した漢方薬を処方します。そのため、同じ病名や症状を抱える2人であっても、「証」が違えば処方される漢方薬が異なることがあります。逆に、まったく異なる症状であっても、「証」が近ければ同じ漢方薬が処方されるケースもあります。
「証」は難しく考え過ぎないで!
定義を見ると「証」は、理解しづらい専門的なもののように思えるかもしれません。ですが、「証」は数ある漢方薬の中から自分に最適な漢方薬を見つけるための指針になるものです。あまり構えず、「自分に合う漢方薬の選び方の1つ」として考えてみてくださいね。
「証」の4つの種類
「証」には、その人の身体が病気や不調とどのように向き合っているかを知る「ものさし」となる、代表的な4つの種類があります。
- 虚実(きょじつ):抵抗力の強さ
- 陰陽(いんよう):刺激への反応
- 寒熱(かんねつ):暑さ・寒さへの耐性
- 表裏(ひょうり):病気の深さ
さらに、それぞれの「証」は、相反する特徴を持つ2つのタイプに分かれます。それぞれの「証」ごとに、当てはまる人の特徴や治療内容について詳しく解説していきます。
虚実:抵抗力の強さ
「虚実(きょじつ)」は、身体の抵抗力の強さをあらわす証です。
抵抗力が強いエネルギッシュな方は「実証(じっしょう)」、反対に身体が弱い方は「虚証(きょしょう)」に該当します。
実証と虚証、それぞれには次のような特徴があります。
| 種類 | 実証 | 虚証 |
|---|---|---|
| 当てはまる人の特徴 |
|
|
| 治療の特徴 | 瀉実(しゃじつ):体内の余分なものを取り除く治療 | 「補虚(ほきょ)」:体内の足りないものを補う治療 |
実証の方が身体が強く、病気にも強い印象があるかもしれません。しかし、どちらか一方に偏りすぎても病気になりやすく、どちらにも偏らない「中間証(ちゅうかんしょう)」の状態が理想とされています。そのため、実証の方は虚証方向へ、虚証の方は実証の方向を目指した治療を行います。
虚証=身体が弱いということではない
実証と虚証は、どちらが良いというものではありません。中間である中間証が最も良いとされているので、虚証に当てはまる方は心配する必要はありませんよ。
陰陽:刺激への反応
「陰陽(いんよう)」は、外部からの刺激(主に暑さ・寒さ)に対する反応を表す「証」です。
活動的で暑がりな方は「陽証(ようしょう)」、非活動的で寒がりな方は「陰証(いんしょう)」に該当します。
陽証と陰証には、それぞれ次のような特徴があります。
| 種類 | 陽証 | 陰証 |
|---|---|---|
| 当てはまる人の特徴 |
|
|
| 治療の特徴 | より作用の強い漢方薬を選んでも身体への負担が少ない。 | 強い漢方薬を服用すると、かえって身体の負担になる。効き目が穏やかで身体への負担が少ない漢方薬を用いる。 |
陽証の方のほうが漢方薬の作用への耐性が高いため、作用の強い漢方薬で症状の改善を狙うのが良いでしょう。一方で、陰証の方は漢方薬の作用で体調を崩す可能性があります。なるべく緩やかに作用していく漢方薬で、体調を整えましょう。
陰陽は、漢方薬の副作用に関わる重要な「証」です。漢方薬を服用しているのに体調が良くならない、悪化したような症状がある場合は、作用の穏やかな漢方薬への変更を検討しましょう。
寒熱:暑さ・寒さへの耐性
暑がりな方は「熱証(ねっしょう)」、寒がりな方は「寒証(かんしょう)」に該当します。暑さ・寒さに関連するため、陰陽と同じような特徴で分けられるため、混同しないように注意が必要です。
熱証と寒証には、それぞれ次のような特徴があります。
| 虚実の種類 | 熱証 | 寒証 |
|---|---|---|
| 当てはまる人の特徴 |
|
|
| 治療の特徴 | 身体の過剰な熱を取り除く治療 | 身体を温める治療 |
陰陽と見極める場合、症状に対する反応の違いがポイントです。例えば、普段暑がりなのに、病気のときは寒さを感じやすい場合は寒証の可能性があります。ただし、個人では見極めが難しいため、専門医に診断してもらうことをおすすめします。
また、熱証と寒証は、普段の生活習慣が重要な判断基準となります。改めて自分がどのように生活しているかを客観的に観察し、メモなどをしておくと、どちらの「証」に当てはまるかが判断しやすくなりますよ。
表裏:病気の深さ
「表裏(ひょうり)」は、病気や不調が身体のどの部分に現れているかを示す証です。
皮膚や髪などの症状が現れている方は「表証(ひょうしょう)」、胃や腸などの症状がある場合は「裏証(りしょう)」に該当します。
表証と裏証には、それぞれ次のような特徴があります。
| 虚実の種類 | 表証 | 裏証 |
|---|---|---|
| 特徴 |
|
|
表証と裏証は、文字から特徴が分かりやすいため、判断しやすいかもしれません。ただし、どちらにも偏らない状態を「半表半裏(はんぴょうはんり)」と呼びます。身体の外と内の間で病気がくすぶっている状態を指し、まだ代表的な症状が現れていない状況のため、判別が難しい・できない状態です。
表裏は確定するとは限らない!
表証と裏証は、身体のどの部分に不調が出ているかを判別する「証」です。ただし、他の「証」とは違って確定しない場合もあるので、無理してどちらかに分けて判断する必要はありません。

病院などでの「証」診断方法

一人ひとりの「証」を特定するために、病院などでは「四診(ししん)」という東洋医学独自の診断方法を用います。これは、五感(目・耳・鼻・口・手)を使って診察を行うもので、患者さんの自覚症状や客観的な症状から総合的に判断し「証」を特定します。
四診は以下の4つで構成されます。
- 望診(ぼうしん):視覚からの情報で、顔色や表情、態度、姿勢、体型などを診ます。特に、舌の状態を見る「舌診(ぜっしん)」が重要です。
- 聞診(ぶんしん):耳と鼻からの情報で、声の大きさやトーン、咳の様子、呼吸音などの音、体臭や口臭といったニオイを確認する。
- 問診(もんしん):患者さんやその家族から、現在の症状、病歴、普段の生活習慣、食べ物の好み、月経の様子など、様々なことを詳しく聞き取ります。
- 切診(せっしん):身体に直接触れて状態を診ます。脈の速さや強さ、身体の熱さを診る「脈診(みゃくしん)」、腹部に触れて痛みや塊がないかを確認する「腹診(ふくしん)」が主な診断です。
漢方医学では、病態は時間とともに変化するものと考えられており、病態の変化とともに「証」も変化する場合があります。そのため、医師は4つの診断情報を総合的に判断し、その時点での最適な「証」を決定します。
また、「証」を正確に診断するために、普段の生活スタイルや習慣、ニキビや胃腸の具合といった、今の症状と関係のない質問をされることがあります。些細な事柄であっても、「証」を見極めるための重要な診察の一部となるため、現在の不調とは関係のない質問にも、正直に、素直に答えることが大切です。
「証」と漢方薬の効果との関係
漢方薬は、西洋医学のように病名に対して処方されるのではなく、その人の「証」に合うものを服用することで、本来の効果を発揮します。
「証」に合わない漢方薬を服用した場合、期待される効果が出ないだけではありません。かえって身体に負担をかけたり、不調を悪化させたりと、副作用を引き起こす可能性もあります。例えば、「実証」向けに処方される漢方薬を「虚証」の人が服用すると、下痢が止まらなくなるなど、より不調になるケースが報告されています。
そのため、医療用漢方製剤の添付文書には、「本剤の使用にあたっては、患者の証(体質・症状)を考慮して投与すること」と記載されています。「証」が漢方薬の有効性や安全性を高める上で、特に重要な項目となっています。
「証」と漢方薬の具体例:十味敗毒湯
ここまで「証」と漢方薬の関係について解説してきましたが、実際にどのように「証」を用いて漢方薬が選ばれているのか、「十味敗毒湯(じゅうみはいどくとう)」を例に解説していきます。
十味敗毒湯は、ニキビや腫れ、湿疹、アトピー性皮膚炎など、肌の不調を整え改善する作用のある漢方薬です。そして、腫れや炎症は熱を帯びた症状となるため、熱証や表証の方の漢方薬に適していると考えられます。
また、十味敗毒湯は比較的作用が強い漢方薬のため、実証や陽証、中間証の方にも処方が検討されます。熱証に当てはまっていても、陰証の方の場合、副作用が現れて皮膚トラブル以外の不調が現れる可能性もあります。そのため、熱証かつ実証の方に十味敗毒湯が最も適していると考えられます。
このように、1つの「証」に該当するからといって、適切な漢方薬であるとは限りません。医師が漢方薬を処方する場合は、診断と豊富な知識の両方を用いて、総合的に判断しながら最適な漢方薬を称します。ですので、私たちが市販の漢方薬を購入するときも「証」を意識して、自分の体質に合う漢方薬を選びましょう。
漢方薬は複数の生薬が配合されているため、配合されている成分の量や種類によって、作用の強さなどが変化します。漢方薬の説明書などを確認し、自分の「証」に合う漢方薬を見つけましょう。
自分の「証」を知る方法
自分の「証」に合った漢方薬を選ぶことは、漢方薬本来の作用を最大限に引き出すことにつながります。そのため、まずは自分の「証」を知ることが大切です。
自分の「証」を知るためには、次のような項目から、普段の過ごし方や生活習慣などを見つめ直し、各「証」の特徴と照らし合わせて考えてみましょう。
「証」を判断するポイント
- 食べ物の好み(温かい・冷たい、味付けなど)
- 睡眠パターン
- 疲労感の出方
- 暑さ・寒さへの反応
- 普段の体調の変化
例えば、体力や抵抗力の強さを測る「虚実」は、体型、声の大きさ、疲労感、肌の状態、食欲などから、自己判別が可能です。「虚実」の紹介で用いた表を活用して、どちらの「証」に当てはまるのか、一度考えてみましょう。
また、「証」を調べる場合、1つに絞ろうとする必要はありません。これは、「証」には合計8種類があり、人によってこれらの「証」が複雑に組み合わさっているからです。1つに絞って「この証だ」と思っても、本当にその判断が正しいのか分かりません。そのため、複数の「証」に当てはまったときは、それぞれが自分の「証」だと判断し、各「証」を考慮しながら漢方薬を選ぶのが良いでしょう。
「証」の判別ポイントは細かく複数に分かれているので、もし判断に迷う場合や正確に知りたいときは、医師や薬剤師、登録販売者といった専門家に相談しましょう。
専門家に「証」の診断を受けるときは、普段の過ごし方や生活習慣なども細かく伝えることが大切です。伝える情報が細かく多いほど、より正確な「証」を判別できるので、普段から上記で紹介したようなポイントなどをメモしておきましょう。
まとめ
漢方治療では、人それぞれの「証」を診断し、その人の「証」に合わせた漢方薬を処方・服用することを大切にしています。
漢方薬は、症状に直接作用する西洋薬とは異なり、その人の体質や全身の状態を整えることで、身体が本来持つ自然治癒力を高めることを目指します。そのため、自分の「証」をきちんと把握することが、最適な健康管理につながります。
また、自分の「証」を正確に把握するためには、専門的な知識と経験が必要です。ぜひ、漢方に詳しい医師や薬剤師などの専門家と相談しながら、自分の「証」を把握しましょう。そして、体質・体調に合った最適な漢方薬を見つけ、健康的な生活を送るために活用してみてくださいね。
よくある質問
- 症状が同じなら、同じ漢方薬が処方されるんですか?
- いいえ、異なる場合があります。漢方医学では、同じ症状であっても「証」が異なれば、処方される漢方薬は異なります。漢方は、症状の奥にある体質や病態全体をとらえて治療する「随証治療(ずいしょうちりょう)」という考え方に基づいているためです。
- 一度診断された「証」は一生変わらないの?
- いいえ、病態は刻々と変化するため、「証」もそれに応じて変化します。また、体調の変化、年齢、季節、環境の変化などの要因によっても「証」は変わることがあります。そのため、その時々の身体の状態に合わせて「証」を再確認し、治療方針を調整することが大切です。
「証」に合わせて十味敗毒湯を服用しよう!
十味敗毒湯は、作用が強い漢方薬のため、実証や陽証、中間証の方が服用するのに適しています。肌トラブルで悩むこれらの「証」の方は、ぜひ専門家に相談して試してみましょう。

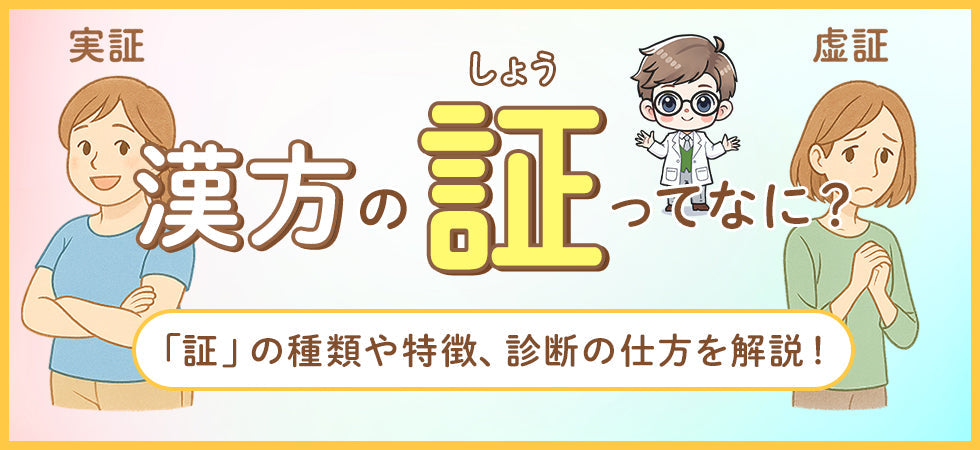












「証」は、漢方薬と自分の身体との相性を考える上で大切なものです。漢方薬で不調を改善するためには、必ず「証」をベースに服用する漢方薬を選択しましょう。