
- この記事はこんな人におすすめ
-
- 漢方薬に興味があるが効果や選び方がわからない
- 慢性的な体の不調を改善したい
- 根本から体質改善を目指したい
「漢方って本当にすごい効果があるの?」
「漢方の効果って西洋薬とは違うの?」
このような疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか?
漢方薬は、実は1500年以上の歴史を持ち、現代の臨床研究でも効果が実証されている医薬品です。
国内でも200種類以上の漢方薬が認められていて、広く使用されています。
本記事では、漢方の「すごい効果」の真実や症状別の選び方について詳しく解説します。
- この記事を読むとわかること
-
- 漢方薬が効く3つの科学的なメカニズムがわかる
- 漢方薬の正しい服用方法と注意点がわかる
- 代表的な漢方処方の効果と使い分けができる
体質に合った漢方で根本改善を
繰り返すニキビや肌トラブルには、外側からのケアだけでは限界があります。そこで注目したいのが、体の内側から整える「十味敗毒湯」です。食事や生活習慣を気をつけていても改善しない肌トラブルには、漢方の力をプラスして内側からの根本ケアを始めてみませんか?
十味敗毒湯について詳しくはこちら
漢方薬とは?西洋薬との違いを知ろう

漢方薬とは、日本で独自に発展した「漢方医学」で使われるくすりを指しています。
自然界に存在する植物や動物、鉱物などの薬効となる部分を「生薬(しょうやく)」と称し、基本的には2つ以上組み合わせてつくられるのが一般的であると日本製薬工業協会でも紹介されています。
漢方薬と西洋薬の効果の違い
漢方薬は、西洋薬では対応しにくい体質や未病段階にも効果が期待できるのが特徴です。 例えば、病院の検査で異常がない体質による症状や、更年期障害などの検査値に現れない体の不調、そして病名がつかない「未病」段階のものに対しても、漢方薬では効果が期待できるのです。
表:漢方薬と西洋薬の違い
| 項目 | 漢方薬 | 西洋薬 |
|---|---|---|
| 治療対象 | 体質の改善 | 病気・症状の改善 |
| 成分 | 複数の生薬 | 単一の化学成分 |
| 効果 | 緩やかで根本的 | 即効性で限定的 |
| 副作用 | 比較的少ない | 特定の副作用あり |
漢方の「気血水」理論
漢方には、体を3つの要素「気血水」で捉える特有の考え方があります。
- 気(き):体のエネルギーや精神力のこと。気が乱れると疲れやすい、やる気が出ない、そしてストレスを感じやすくなる
- 血(けつ):血液の流れや栄養の巡りのこと。血が乱れると冷え性、肌荒れ、生理不順などが起こる
- 水(すい):体内の水分バランスのこと。水が乱れるとむくみ、下痢、めまいなどの症状があらわれる
これらの3つの要素のどの部分が乱れているかを見極めて漢方薬を選ぶことで、症状の根本的な改善が期待できます。
漢方薬は長く飲まないと効かないものばかりではない!
漢方薬の中にも即効性が期待できるものもあります。例えば、こむら返りに効果が期待できる芍薬甘草湯は、早くて5分で痙攣を抑えることができます。
漢方薬はなぜ効くのか?3つのメカニズム

漢方薬は、西洋薬にはない「すごい効果」があります。
具体的には、「異病同治」や「病気ではなく病人をみる」考えのもとで、体質から根本改善する効果を期待できます。
ここでは漢方薬のすごい効果3つの主なメカニズムを紹介します。
異病同治による複数の症状へのアプローチ
漢方薬には「異病同治」と呼ばれる固有の特性があります。
一見無関係な症状でも、同じ根本原因から生じていて、一つの処方で様々な不調を改善できる考え方です。
例えば、風邪薬として有名な葛根湯は、「体表部の緊張と冷え」から生じる肩こり、頭痛などにも効果が期待できます。
体質改善による根本治療
漢方医学は「病気ではなく病人をみる」考えをもとに、症状を抑えるのではなく、体が本来持つ自然治癒力を高めることを目指します。
体に不足している栄養素を生薬で補い、気血水のバランスを整えることで、健康状態を根本から立て直すことができるのです。
一人一人に合わせた個別化治療
漢方では同じ症状でも、患者の体質や腸内環境によって最適な処方が変わります。
漢方薬の有効成分の多くは配糖体として存在し、腸内細菌によって代謝されることで効果を発揮します。
漢方が効かない場合の多くは、体質に合わない処方を使用しているため、体質に合わせた漢方を選ぶといいでしょう。
漢方薬の正しい飲み方と注意点
漢方薬は、複数の生薬を配合して作られる特性上、服用タイミングや注意点が西洋薬とは異なる部分があります。
ここでは漢方薬の正しい服用方法と注意点を解説していきます。
漢方薬は食前または食間に服用する
漢方薬は、食前または食間に服用することが基本です。
食前は「食事の30分前」、食間は「食後2〜3時間後」の食事と食事の間を指します。
食後が多い西洋薬とは異なり、漢方は空腹時に吸収率が高くなるものが多いです。
漢方薬の副作用と注意点
漢方薬は天然由来とはいえ医薬品であるため、副作用にも注意が必要です。
皮疹・発疹、かゆみ、顔や唇の腫れなどが現れた場合は、すぐに服用を中止しましょう。
また、複数の漢方薬を併用する際は、同じ成分の重複摂取の可能性があるため、必ず医師や薬剤師に相談するようにしましょう。
症状別のおすすめ漢方薬【代表的な5処方】
症状や体質によって適切な処方が変わります。
ここでは、代表的な漢方薬を5つ紹介します。
ぜひ自分自身の症状や体質をしっかりと見極めて、適切な漢方薬を選ぶようにしましょう。
葛根湯(かっこんとう)
葛根湯は、風邪の初期症状や首肩のこわばりに即効性を期待できます。
体力のある方にはおすすめです。
十味敗毒湯(じゅうみはいどくとう)
十味敗毒湯は、抗炎症作用と血行促進作用により、ニキビや蕁麻疹、赤ら顔などの化膿性の皮膚疾患に効果的です。
体内に溜まった余分な熱を発散させることで炎症を抑制します。
特に繰り返すニキビや慢性的な皮膚炎症に悩む方に適しており、塗り薬では改善が難しい深部からの炎症にもアプローチできるのが特徴です。
加味逍遙散(かみしょうようさん)
加味逍遙散はPMSや更年期障害などの女性の心身バランスを整える役割が期待できます。
五苓散(ごれいさん)
五苓散は、体内の水分バランスを調整する役割を果たし、二日酔いのむくみや頭痛に効果を期待できます。
当帰飲子(とうきいんし)
当帰飲子は、血を補い肌に潤いを与える「養血潤燥」により、慢性的なかゆみやインナードライに効果を期待できます。
特に年齢とともに起こる肌の乾燥や季節性の乾燥肌、ホルモンバランスの変化による肌トラブルにおすすめです。
内側から肌の保湿機能を高めることで根本的な改善を図ります。
| 漢方薬 | 適応症状 | 特徴 |
|---|---|---|
| 葛根湯 | 風邪の初期、肩こり、頭痛 | 発汗・解熱・鎮痛作用 |
| 十味敗毒湯 | ニキビ、湿疹、じんましん | 体内の熱を冷まし、炎症を鎮める |
| 加味逍遙散 | PMS、更年期障害、うつ症状 | ホルモンバランスと精神状態を整える |
| 五苓散 | むくみ、頭痛、二日酔い | 体内の水分バランスを整える |
| 当帰飲子 | 乾燥肌、かゆみ、貧血 | 血行を促進し、肌に栄養と潤いを供給する |
まとめ
「何もやっても治らない…」
そんな繰り返す肌トラブルに悩んでいませんか?
漢方薬は、肌トラブルの原因であるホルモンバランスを調整することや血行促進、炎症を起こしやすい体質改善といった体の内側からのアプローチができるのが大きな特徴です
繰り返すニキビにも内側からの根本ケアを
化膿しやすいニキビには、体内の熱を冷ます「十味敗毒湯」がおすすめです。10種類もの自然由来の生薬が配合されていて、体の内側からじっくりと働きかけます。

「本当に効果がある?」「どのくらいの期間で変化が感じられる?」「飲みやすさはどう?」といった疑問をお持ちの方は、ぜひ実際の使用者の詳しい体験談を参考にしてみてください。
よくある質問
- 漢方薬はどのくらいで効果が出ますか?
- 急性症状なら数時間から数日程度、慢性症状の改善だと2−4週間程度を目安に考えておくのがいいでしょう。
ただし、体質や症状により個人差があります。 - 漢方薬を西洋薬と一緒に飲んでも大丈夫?
- 基本的に漢方薬と西洋薬は一緒に飲んでも問題ありません。
ただし、一部の漢方薬と西洋薬では、飲み合わせがよくないものもあるため、医師や薬剤師に確認してから一緒に飲むことをおすすめします。
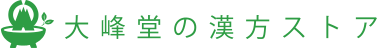














(薬剤師:5年)
漢方薬は体質に合わせて選ぶことで、根本から不調の改善が期待できます。「なんとなく体の調子が悪い」「病院に行くほどではないけれど気になる症状」には漢方の考え方が有効です。ぜひ本記事を読んで、健やかな毎日の第一歩を踏み出していただけると幸いです。