
- この記事はこんな人におすすめ!
-
- 粘膜の乾燥に効果的な漢方薬が知りたい
- 粘膜が乾燥する原因を知りたい
- 更年期のドライシンドロームについて知りたい
- 更年期におすすめの乾燥対策が知りたい
- この記事を読むとわかること
-
- 粘膜の乾燥を改善する漢方薬がわかる
- 粘膜が乾燥する原因がわかる
- ドライシンドロームの原因や症状がわかる
- 更年期が取り組むとよい乾燥対策がわかる
粘膜の乾燥症状|ドライシンドロームとは?

ドライシンドロームとは、一言でいうと「涙や唾液などを分泌する“外分泌腺”の働きが弱まっている状態」のことを言います。
次の5つの部位に乾燥を感じる方は、粘膜が乾いてドライシンドロームになっている可能性があります。
| 部位・名称 | 主な症状 |
|---|---|
| 鼻(ドライノーズ) | カサカサする、ムズムズする、ピリピリ痛む、鼻をかみたくなる、カサブタができる |
| 口(ドライマウス) | 乾く、ネバネバする、口臭が気になる、舌がヒリヒリする、美味しく感じない、飲み込みづらい |
| 目(ドライアイ) | 乾く、かすむ、疲れやすい、充血する、痒くなる、ゴロゴロする |
| 肌(ドライスキン) | カサカサする、ピリピリ痛む、赤みが目立つ、肌荒れしやすい、化粧ノリが悪い |
| 膣(ドライバジャイナ) | ヒリヒリする、膣がかゆい、膣が痛む、性行痛がある、違和感を感じる |
30代後半〜40代前半のプレ更年期から、少しずつ「女性ホルモン(エストロゲン)」が減少します。エストロゲンが減ると自律神経が乱れやすくなるため、全身が乾くようになります。この「全身の乾き」を一つの症候群として考えるようになったのが「ドライシンドローム(乾燥症候群)」です。
ドライシンドロームは男性にも発症する
ストレスが溜まり自律神経が乱れると、男性もドライシンドロームを発症することがあります。目が乾いてゴロゴロする場合は「ドライアイ」、口の中が乾いて痛い・ネバネバする場合は「ドライマウス」の可能性があります。
【部位別】粘膜の乾燥を改善する漢方薬
ドライシンドロームのような粘膜の乾燥には、治療として漢方薬が用いられることがあります。ここでは、鼻、口、目などの部位別に、身体の内側から潤いを与える漢方薬をご紹介します。
鼻(ドライノーズ)を潤す漢方薬
ドライノーズの改善が期待できる「辛夷清肺湯(しんいせいはいとう)」は、呼吸器に潤いを与える漢方薬です。主に慢性鼻炎、蓄膿症、鼻づまりなどの治療で使われていて、鼻粘膜の乾燥や炎症を抑える作用があります。
口(ドライマウス)を潤す漢方薬
ドライマウスの改善が期待できる漢方薬は「麦門冬湯(ばくもんどうとう)」や「白虎加人参湯(びゃっこかにんじんとう)」などが挙げられます。それぞれの特徴は次のとおりです。
| 名前 | 特徴 |
|---|---|
| 麦門冬湯(ばくもんどうとう) | 粘膜や気道を潤し、身体に栄養を届ける機能を高める漢方薬。ドライマウス、から咳、気管支炎などの治療で使われています。 |
| 白虎加人参湯(びゃっこかにんじんとう) | 喉の渇き、更年期のほてり、熱中症の改善などに効果がみられる漢方薬。体の熱を冷まし、潤いを与える生薬が配合されています。 |

しわがれ声やから咳などが気になる場合は「麦門冬湯(ばくもんどうとう)」を。常に水を飲みたくなるような口の渇きがある場合は「白虎加人参湯(びゃっこかにんじんとう)」を選ぶとよいでしょう。
目(ドライアイ)を潤す漢方薬
ドライアイの改善が期待できる「杞菊地黄丸(こぎくじおうがん)」は、目の疲れ、乾燥、充血などの治療に用いられる漢方薬です。配合されている枸杞(クコ)や菊花(キク)などの生薬は、古くから中国で「健康によい」「目によい」とされています。
肌(ドライスキン)を潤す漢方薬
ドライスキンの改善が期待できる漢方薬は「当帰飲子(とうきいんし)」「温清飲(うんせいいん)」「十全大補湯(じゅうぜんだいほとう)」などが挙げられます。それぞれの特徴は次のとおりです。
| 名前 | 特徴 |
|---|---|
| 当帰飲子(とうきいんし) | 皮脂の減少により乾燥した肌に、潤いと栄養を与える漢方薬。ドライスキンによる乾燥、かゆみ、湿疹などの治療に用いられます。 |
| 温清飲(うんせいいん) | 肌のかさつき、赤み、かゆみなどの治療に用いられる漢方薬。体内の熱を取り除き、炎症を抑えながら肌の乾燥を和らげます。 |
| 十全大補湯(じゅうぜんだいほとう) | 全身の疲労や衰弱をサポートする漢方薬。手足の冷えをともなう乾燥肌や、貧血、胃腸の不調などの治療に用いられます。 |

更年期のドライスキンは、肌に潤いと栄養を与える「当帰飲子(とうきいんし)」を。月経不順や更年期障害などもあわせて改善したい場合は、体内の熱を取り除く作用がある「温清飲(うんせいいん)」を選ぶとよいでしょう。
膣(ドライバジャイナ)を潤す漢方薬
ドライバジャイナの改善が期待できる漢方薬は「清心蓮子飲 (せいしんれんしいん) 」や「竜胆瀉肝湯(りゅうたんしゃかんとう)」などが挙げられます。
清心蓮子飲は、尿トラブルのほか、不安感・イライラなどの精神症状もともなう場合に効果的。竜胆瀉肝湯は、泌尿器の炎症やおりものなどの症状がある場合の治療に用いられます。
全身の乾きには、内側から潤いを
身体を潤す10の生薬を配合した『当帰飲子(とうきいんし)』は、ドライスキンのような慢性的な皮膚の乾燥・かゆみを内側から改善する漢方薬です。クリームでは治りきらないカサカサやヒリヒリを、身体の内側からゆるやかに改善します。

こんなお悩みございませんか?
- 自分の症状に効くのか心配
- 効果が出るのにどれくらいかかる?
- 他の薬と併用して飲んでも大丈夫?など
漢方の分野に特化した薬剤師が対応します
購入前、購入後で気になることがあれば、お問い合わせください
粘膜の乾燥|ドライシンドロームの3つの原因

ドライシンドロームには、次の3つの原因があります。
- プレ更年期・更年期
- ストレス
- 血や水の不足
ご自身に当てはまるものがあるか、以下で詳しく見てみましょう。
原因1:プレ更年期・更年期
次の年代の方は、エストロゲンの減少からドライシンドロームの症状があらわれやすい傾向です。
| プレ更年期 | 30代後半〜40代前半 |
|---|---|
| 更年期 | 45歳〜55歳(閉経前後の10年間) |
プレ更年期・更年期の症状には個人差があり、ドライシンドロームのほかには「イライラ」や「冷え」などを感じることがあります。

ドライシンドロームは、20代〜30代前半の若い方でも発症することがあります。ストレスにより自律神経が乱れないように、規則正しい生活をしたりリラックスタイムをつくったりして、早めにストレス&乾燥ケアを始めましょう。
原因2:ストレス
外分泌腺の働きを調整する「自律神経」は、ストレスが原因で乱れることもあります。
たとえば次のような悩みがある方は、自分が思っている以上にストレスが溜まっているかもしれません。
息苦しい
食欲がない
不眠気味
疲れやすい
耳鳴りがする
めまいがする
肌荒れしやすい
やる気が起きない
自律神経の不調はさまざまな病気の原因となるため、早めに解消・改善する必要があります。
ストレスの原因をすぐに取り除くのが難しい場合は、まず「質の高い睡眠」「栄養のある食事」「適度な運動」の3つを心がけましょう。
原因3:血や水の不足
漢方の世界では、人の身体は次の3つで構成されていると考えられています。
| 気(き) | エネルギー |
|---|---|
| 血(けつ) | 血液 |
| 水(すい) | 水分 |
この3つのバランスが崩れると、身体のどこかに不調が生じます。
ドライシンドロームの場合は「血」と「水」の不足が、全身に乾燥を引き起こす原因となっているのです。
「血」は女性が不足しがちな要素
漢方の世界で血液をあらわす「血」は、生理、妊娠、出産などが原因で不足することがあります。栄養不足や加齢によっても血が不足しやすいため、貧血や立ちくらみなどに悩んでいる女性は早めに血を補いましょう。

血を補うには、鉄分、たんぱく質、ビタミン、ミネラルを豊富に含む食品を摂るのがおすすめです!レバーやほうれん草、ピーマン、大豆製品などを日常の食卓に取り入れてみましょう◎
粘膜の潤いケア◎今日からできる乾燥対策3つ

粘膜に潤いを与えるためには、漢方薬で治療するほかに、日々の生活に簡単な乾燥対策を取り入れることが大切です。ここでは、今日からできる乾燥対策を3つご紹介します。
こまめに水分補給をする
もっとも簡単な乾燥対策として「こまめな水分補給」がおすすめです。粘膜に直接潤いを与えることで、喉や口内の乾燥対策につながります。
ただし、水分を一度に大量にとると頭痛やめまいなどの「水中毒(低ナトリウム血症)」を引き起こすリスクがあるため、こまめに摂取するように心がけましょう
水分摂取量の目安は2.3〜3.5L
厚生労働省によると、水分摂取量の目安は活動レベルの少ない人で2.3〜2.5L。活動レベルの高い人で3.3〜3.5Lが目安と推定されています。健康的な成人で体重1kgあたり約35mlが「1日に必要な水分量」と言われているため、自分の体重や活動レベル、年齢などに適した水分量を摂取しましょう。

運動の途中や入浴のあと、就寝の前後などは水分が不足しやすい状態です。喉の渇きはすでに「脱水」が始まっている証拠なので、渇きを感じる前にこまめな水分補給を心がけましょう◎
粘膜の健康によい栄養を摂る
粘膜の潤いを保つためには、皮膚や粘膜の潤いを維持するビタミンAや、角質層の水分保持するセラミドなどの「粘膜の健康によい栄養」を積極的に摂ることが大切です。具体的な食材は次の表のとおりです。
| 栄養 | 食材 |
|---|---|
| ビタミンA | レバー、卵、うなぎ、あなご、にんじん、ほうれん草、モロヘイヤ ……など |
| ビタミンC | じゃがいも、ピーマン、ブロッコリー、いちご、キウイ、赤パプリカ ……など |
| セラミド | こんにゃく、大豆、黒豆、小豆、ひじき、わかめ、ほうれん草、黒ごま ……など |
| 亜鉛 | 牡蠣、豚レバー、牛肉、卵、チーズ、納豆、アーモンド、落花生 ……など |
| 鉄分 | レバー、赤身肉、赤身魚、小松菜、ほうれん草、ひじき、パセリ、ココア ……など |
ビタミンCはコラーゲンの生成を促し、セラミドは角質層の水分を保持する役割があります。亜鉛や鉄分も粘膜の健康には欠かせない栄養のため、日々の食事に少しずつ取り入れていきましょう。

鉄分の吸収率をあげるには、ビタミンCを豊富に含むブロッコリーやじゃがいも、たんぱく質が豊富な肉・魚・卵などを一緒に摂ると効率的です◎
加湿器やマスクで乾燥を防ぐ
加湿器やマスクで鼻・喉の乾燥を防ぐのも、粘膜の乾燥対策におすすめです。厚生労働省の「建築物環境衛生管理基準」によると、室内の快適な湿度は40〜70%が目安とされています。
また、マスクは鼻や喉を乾燥から守るだけでなく、吐いた息に含まれる水分を外へ逃さない効果も期待できます。夏場にマスクをつけると熱中症のリスクが高まるため、季節や状況に応じて着用しましょう。
当帰飲子でドライシンドロームを改善
当帰飲子は、体内の「血」と「水」のバランスを整え、全身に潤いを補います。掻きむしりたくなるような肌の乾燥や、血行不良による全身の冷えを生薬の力でやさしく改善していく漢方薬です。


まとめ
ドライシンドロームは、プレ更年期〜更年期(30代後半〜55歳くらい)に起こりやすい乾燥症状です。
ストレスや血・水の不足でもドライシンドロームを引き起こすことがあるため、質の高い睡眠、栄養のある食事、適度な運動の3つをなるべく心がけて過ごすようにしてみてください。
生活習慣を見直しても改善がみられない場合は、ドライシンドロームの症状に応じて内科、眼科、歯科などの医療機関を受診しましょう。
よくある質問
- 粘膜が弱い人の特徴は?
- 粘膜が弱い人の特徴は、喘息がある、花粉症がある、口呼吸が多い、胃腸が弱い、免疫力が低下しているなどが挙げられます。ストレスを抱えて自律神経が乱れている場合も、粘膜が弱くなったり、乾燥したりしやすくなります。
- 粘膜の乾燥(ドライシンドローム)はサプリで治せる?
- 粘膜の乾燥(ドライシンドローム)は「サプリだけで治せる」とは言い切れません。なかにはドライシンドロームの原因である女性ホルモンの減少、ストレス、血・水の不足などにアプローチできるものもありますが、サプリはあくまで「補助的な役割」として捉えておきましょう。
- ドライシンドロームは何科に行けばいい?
- ドライシンドロームは症状に応じて適切な診療科が異なります。ドライアイは眼科、ドライマウスは歯科・口腔外科、ドライスキンは皮膚科、ドライノーズは耳鼻咽喉科、ドライバジャイナは婦人科の受診が一般的です。
- ドライマウスは漢方で治せる?
- ドライマウスは、漢方薬の服用で自覚症状の改善がみられたデータがあります。J-Stageの「口腔乾燥症に対する麦門冬湯の臨床効果」によると、漢方薬の「麦門冬湯(ばくもんどうとう)」を1か月間服用した54歳〜82歳の女性16名のうち、13名(81%)が自覚症状としてドライマウスの改善を認めています。
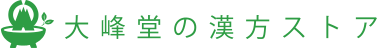


 更年期に体が痒いのは肌トラブルだけが問題ではない?原因と対処法を紹介
更年期に体が痒いのは肌トラブルだけが問題ではない?原因と対処法を紹介

目や口などの「粘膜の乾燥」に悩んでいませんか?単純なドライアイやドライマウスの場合もありますが、複数の部位に乾燥を感じる場合は「ドライシンドローム」を引き起こしている可能性があります。ドライシンドロームはプレ更年期から悩みがちな乾燥症状の一つなので、ぜひ本記事で原因や乾燥対策をチェックしてみましょう。